糖尿病
糖尿病は、血糖値が高い状態が続く病気です。
初期には自覚症状がほとんどないため、気づかないうちに進行し、神経障害、腎症、網膜症などの合併症を引き起こし、最終的には心筋梗塞や脳卒中といった命に関わる病気の原因となることがあります。
初期には自覚症状がほとんどないため、気づかないうちに進行し、神経障害、腎症、網膜症などの合併症を引き起こし、最終的には心筋梗塞や脳卒中といった命に関わる病気の原因となることがあります。
チェックリスト
糖尿病チェックリスト
- ご飯、パン、麺類など炭水化物中心の食事が好きでよく食べる
- 甘い飲み物(清涼飲料水、缶コーヒーなど)を日常的に飲む
- 野菜やきのこ、海藻類をあまり食べない
- 肥満気味である、または内臓脂肪が多いと指摘されたことがある
- 運動不足である
- 喫煙の習慣がある
- 飲酒量が多い
- ストレスが多いと感じる、または睡眠不足が続いている
- 家族に糖尿病の人がいる(特に親や祖父母)
- 健診で血糖値が高い、またはHbA1cが高いと指摘されたことがある
糖尿病とは
糖尿病は、血液中のブドウ糖(血糖)の濃度が高い状態、つまり「高血糖」が慢性的に続く病気です。
私たちの体は、食事から得たブドウ糖をエネルギー源として利用していますが、このブドウ糖が細胞に取り込まれるためには、膵臓から分泌されるインスリンというホルモンが不可欠です。
糖尿病は、このインスリンが十分に働かないために起こります。
糖尿病は、インスリンの作用不足の原因によって、大きく1型糖尿病と2型糖尿病、そしてその他の特定の原因による糖尿病、妊娠糖尿病に分類されます。それぞれのタイプによって、発症のメカニズムや治療法が異なります。
私たちの体は、食事から得たブドウ糖をエネルギー源として利用していますが、このブドウ糖が細胞に取り込まれるためには、膵臓から分泌されるインスリンというホルモンが不可欠です。
糖尿病は、このインスリンが十分に働かないために起こります。
糖尿病は、インスリンの作用不足の原因によって、大きく1型糖尿病と2型糖尿病、そしてその他の特定の原因による糖尿病、妊娠糖尿病に分類されます。それぞれのタイプによって、発症のメカニズムや治療法が異なります。
インスリンの役割
インスリンは、体内で唯一血糖値を下げるホルモンです。食事をすると血糖値が上昇しますが、インスリンが分泌されることで、血液中のブドウ糖が肝臓や筋肉、脂肪細胞に取り込まれ、エネルギーとして利用されたり、貯蔵されたりします。これにより、血糖値は適切な範囲に保たれます。インスリンの働きが不十分になると、ブドウ糖が細胞に取り込まれず、血液中に溢れてしまい、高血糖の状態が続くことになります。
糖尿病の種類
糖尿病は、その発症メカニズムによって主に以下のタイプに分けられます。
1型糖尿病
1型糖尿病は、自己免疫反応などによって、膵臓のインスリンを分泌する細胞(β細胞)が破壊され、インスリンがほとんど、または全く作られなくなる病気です。通常は子どもや若い人に突然発症することが多く、生活習慣とは直接的な関係がありません。発症すると、血糖値をコントロールするためにインスリン注射が必須となります。インスリンがないと生命を維持できないため、生涯にわたるインスリン補充療法が必要となります。日本では糖尿病患者全体の数%とされています。
1型糖尿病は、自己免疫反応などによって、膵臓のインスリンを分泌する細胞(β細胞)が破壊され、インスリンがほとんど、または全く作られなくなる病気です。通常は子どもや若い人に突然発症することが多く、生活習慣とは直接的な関係がありません。発症すると、血糖値をコントロールするためにインスリン注射が必須となります。インスリンがないと生命を維持できないため、生涯にわたるインスリン補充療法が必要となります。日本では糖尿病患者全体の数%とされています。
2型糖尿病
2型糖尿病は、糖尿病患者の約9割を占める最も一般的なタイプです。インスリンの分泌量が不足するか、またはインスリンは分泌されているのにその働きが悪くなる「インスリン抵抗性」によって引き起こされます。インスリン抵抗性とは、細胞がインスリンの作用を受けにくくなる状態を指します。2型糖尿病は、遺伝的な要因に加えて、肥満、運動不足、過食、ストレスなどの生活習慣が深く関わって発症します。中高年で発症することが多いですが、近年では食生活の欧米化や運動不足により、若年層でも増加傾向にあります。初期には症状がほとんどなく、健康診断などで偶然発見されることが多いです。
2型糖尿病は、糖尿病患者の約9割を占める最も一般的なタイプです。インスリンの分泌量が不足するか、またはインスリンは分泌されているのにその働きが悪くなる「インスリン抵抗性」によって引き起こされます。インスリン抵抗性とは、細胞がインスリンの作用を受けにくくなる状態を指します。2型糖尿病は、遺伝的な要因に加えて、肥満、運動不足、過食、ストレスなどの生活習慣が深く関わって発症します。中高年で発症することが多いですが、近年では食生活の欧米化や運動不足により、若年層でも増加傾向にあります。初期には症状がほとんどなく、健康診断などで偶然発見されることが多いです。
その他の特定の原因による糖尿病
稀に、特定の病気や薬剤が原因で糖尿病を発症することがあります。
稀に、特定の病気や薬剤が原因で糖尿病を発症することがあります。
- 遺伝子異常による糖尿病 遺伝子の異常によってインスリンの分泌や働きに問題が生じるタイプです。
- 膵臓の病気による糖尿病 慢性膵炎、膵臓がん、膵臓手術などによって膵臓がダメージを受け、インスリンの分泌が低下することで発症します。
- ホルモンの異常による糖尿病 副腎皮質ホルモンが過剰に分泌されるクッシング症候群や、成長ホルモンが過剰に分泌される先端巨大症など、血糖値を上げるホルモンが原因で糖尿病になることがあります。
- 薬剤による糖尿病 ステロイド薬、一部の免疫抑制剤、抗精神病薬などの副作用として血糖値が上昇し、糖尿病を発症することがあります。
糖尿病の原因
糖尿病の主な原因は、遺伝的な要因と、日々の生活習慣が複雑に絡み合って起こると考えられています。特に、過食や運動不足による肥満、ストレスなどが血糖値を適切に保つインスリンの働きを阻害し、糖尿病の発症に深く関わっています。
糖尿病の原因は、そのタイプによって異なりますが、特に患者数の多い2型糖尿病では、遺伝と生活習慣が密接に関わっています。
糖尿病の原因は、そのタイプによって異なりますが、特に患者数の多い2型糖尿病では、遺伝と生活習慣が密接に関わっています。
遺伝的要因
糖尿病は、遺伝的な体質が大きく関与する病気です。家族(特に親や祖父母)に糖尿病の人がいる場合、遺伝的にインスリンの分泌能力が低い、あるいはインスリンが効きにくい(インスリン抵抗性が高い)体質を受け継いでいる可能性があります。このような遺伝的素因を持つ人が、次に述べるような生活習慣の乱れを続けると、糖尿病を発症しやすくなります。ただし、遺伝的素因があるからといって必ず糖尿病になるわけではありません。生活習慣に注意することで発症を遅らせたり、予防したりすることが可能です。
生活習慣
2型糖尿病の発症には、現代社会の食生活やライフスタイルの変化が深く関わっています。
食事
食生活は血糖値に直接的な影響を与えます。
過食
必要以上に食べ過ぎることで、摂取カロリーが消費カロリーを上回り、肥満に繋がります。特に炭水化物(糖質)や脂質の過剰な摂取は、血糖値の急上昇を招き、膵臓のインスリン分泌に大きな負担をかけます。
食生活は血糖値に直接的な影響を与えます。
過食
必要以上に食べ過ぎることで、摂取カロリーが消費カロリーを上回り、肥満に繋がります。特に炭水化物(糖質)や脂質の過剰な摂取は、血糖値の急上昇を招き、膵臓のインスリン分泌に大きな負担をかけます。

高GI(グリセミックインデックス)食品の摂取
白米、白いパン、麺類、清涼飲料水、菓子類など、消化吸収が早く、食後の血糖値を急激に上げる食品(高GI食品)を頻繁に摂ることは、血糖コントロールを悪化させ、インスリンに過剰な負担をかけます。
食物繊維不足
野菜、きのこ、海藻類などに多く含まれる食物繊維は、糖の吸収を緩やかにし、食後の血糖値の急上昇を抑える働きがあります。食物繊維が不足すると、血糖値が不安定になりやすくなります。
運動不足
運動不足は、糖尿病の大きな原因の一つです。
インスリン抵抗性の悪化
運動は、筋肉がブドウ糖を消費する量を増やし、インスリンの働きを改善する効果があります。運動不足になると、筋肉での糖の利用が低下し、インスリン抵抗性が高まり、血糖値が下がりくくなります。
白米、白いパン、麺類、清涼飲料水、菓子類など、消化吸収が早く、食後の血糖値を急激に上げる食品(高GI食品)を頻繁に摂ることは、血糖コントロールを悪化させ、インスリンに過剰な負担をかけます。
食物繊維不足
野菜、きのこ、海藻類などに多く含まれる食物繊維は、糖の吸収を緩やかにし、食後の血糖値の急上昇を抑える働きがあります。食物繊維が不足すると、血糖値が不安定になりやすくなります。
運動不足
運動不足は、糖尿病の大きな原因の一つです。
インスリン抵抗性の悪化
運動は、筋肉がブドウ糖を消費する量を増やし、インスリンの働きを改善する効果があります。運動不足になると、筋肉での糖の利用が低下し、インスリン抵抗性が高まり、血糖値が下がりくくなります。
肥満の進行
エネルギー消費が少ないため、摂取したカロリーが消費されずに脂肪として蓄積され、肥満に繋がります。肥満は、前述の通りインスリン抵抗性を高める主要な原因です。
肥満
特に内臓脂肪型肥満は、糖尿病の最も重要なリスク因子の一つです。内臓脂肪からは、インスリンの働きを妨げる物質(悪玉アディポサイトカイン)が分泌され、インスリン抵抗性を引き起こします。また、炎症性サイトカインも分泌され、慢性的な炎症が全身のインスリン感受性を低下させます。
エネルギー消費が少ないため、摂取したカロリーが消費されずに脂肪として蓄積され、肥満に繋がります。肥満は、前述の通りインスリン抵抗性を高める主要な原因です。
肥満
特に内臓脂肪型肥満は、糖尿病の最も重要なリスク因子の一つです。内臓脂肪からは、インスリンの働きを妨げる物質(悪玉アディポサイトカイン)が分泌され、インスリン抵抗性を引き起こします。また、炎症性サイトカインも分泌され、慢性的な炎症が全身のインスリン感受性を低下させます。

喫煙・飲酒
喫煙は、インスリンの働きを阻害し、血糖値を上昇させるだけでなく、血管を傷つけ、糖尿病の合併症(動脈硬化、神経障害など)を悪化させます。喫煙者は非喫煙者に比べて糖尿病を発症するリスクが高いことが知られています。
過度な飲酒は、肝臓に負担をかけ、血糖コントロールを乱すことがあります。アルコール自体にカロリーがあるため、過剰な飲酒は肥満の原因にもなります。
喫煙は、インスリンの働きを阻害し、血糖値を上昇させるだけでなく、血管を傷つけ、糖尿病の合併症(動脈硬化、神経障害など)を悪化させます。喫煙者は非喫煙者に比べて糖尿病を発症するリスクが高いことが知られています。
過度な飲酒は、肝臓に負担をかけ、血糖コントロールを乱すことがあります。アルコール自体にカロリーがあるため、過剰な飲酒は肥満の原因にもなります。
その他の原因
稀に、特定の病気や薬剤が原因で糖尿病が発症することもあります。
膵臓の病気
膵炎や膵臓の手術などにより、インスリンを分泌する細胞が破壊されることがあります。
ホルモン異常
副腎皮質機能亢進症(クッシング症候群)、先端巨大症など、血糖値を上げるホルモンが過剰に分泌される病気です。
薬剤性
ステロイド剤、一部の降圧剤、免疫抑制剤などの長期使用が血糖値を上昇させることがあります。
これらの原因による糖尿病は「二次性糖尿病」と呼ばれ、原因となっている病気の治療や薬剤の変更によって改善する可能性があります。
膵臓の病気
膵炎や膵臓の手術などにより、インスリンを分泌する細胞が破壊されることがあります。
ホルモン異常
副腎皮質機能亢進症(クッシング症候群)、先端巨大症など、血糖値を上げるホルモンが過剰に分泌される病気です。
薬剤性
ステロイド剤、一部の降圧剤、免疫抑制剤などの長期使用が血糖値を上昇させることがあります。
これらの原因による糖尿病は「二次性糖尿病」と呼ばれ、原因となっている病気の治療や薬剤の変更によって改善する可能性があります。
糖尿病の症状
糖尿病は、初期にはほとんど自覚症状がないため、「サイレントキラー(静かなる殺し屋)」とも呼ばれます。血糖値がかなり高くなっても、体がその状態に慣れてしまい、異常を感じにくいことが多いのです。しかし、高血糖の状態が長く続くと、次第に全身の血管や神経がダメージを受け、様々な症状や合併症が現れてきます。
糖尿病の症状は、血糖値が非常に高くなった場合に現れる「典型的な症状」と、血糖コントロールが悪い状態が長期間続くことで現れる「合併症による症状」に分けられます。
糖尿病の症状は、血糖値が非常に高くなった場合に現れる「典型的な症状」と、血糖コントロールが悪い状態が長期間続くことで現れる「合併症による症状」に分けられます。
糖尿病の典型的な症状
血糖値が非常に高くなると、体は余分な糖を尿として排出しようとします。それに伴い、以下のような症状が現れることがあります。これらの症状が出ている場合は、かなり糖尿病が進行している可能性があります。
- 喉が異常に渇く(口渇)
- 尿の量が増える・回数が増える(多尿)
- 体重が減る(急な体重減少)
- 疲れやすい・倦怠感
- 皮膚が乾燥しやすい・かゆみ
- 手足のしびれ、感覚の鈍化
- 目がかすむ・視力低下
- 感染症にかかりやすい・治りにくい
糖尿病の合併症による症状
糖尿病の典型的な症状が現れなくても、高血糖状態が長く続くと、全身の血管や神経がダメージを受け、様々な合併症が進行します。これらの合併症によって、初めて深刻な症状が現れることがほとんどです。
糖尿病の三大合併症
特に注意すべきは、糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症の「三大合併症」です。
特に注意すべきは、糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症の「三大合併症」です。
①糖尿病性神経障害
高血糖によって末梢神経がダメージを受け、様々な症状が現れます。
高血糖によって末梢神経がダメージを受け、様々な症状が現れます。
- しびれ、痛み、感覚の鈍化
足の裏や指先がピリピリしびれたり、ジンジンと痛んだり、逆に熱さや冷たさを感じにくくなったりします。重症化すると、傷に気づかず悪化したり、壊疽(えそ)に繋がることもあります。 - 自律神経の障害
立ちくらみ、便秘や下痢、発汗異常、勃起障害(ED)、胃もたれ、排尿障害など、全身の様々な臓器に影響が出ます。
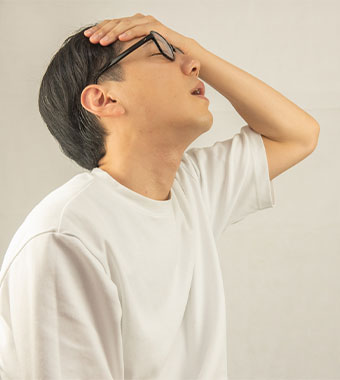
②糖尿病性腎症
高血糖が腎臓の細い血管を傷つけ、腎臓の機能が低下する病気です。
初期には症状がありませんが、進行すると尿にタンパク質が漏れるようになり(タンパク尿)、むくみ、倦怠感などが現れます。
さらに悪化すると、老廃物が体内に蓄積し、最終的には人工透析が必要となる「末期腎不全」に至ります。
高血糖が腎臓の細い血管を傷つけ、腎臓の機能が低下する病気です。
初期には症状がありませんが、進行すると尿にタンパク質が漏れるようになり(タンパク尿)、むくみ、倦怠感などが現れます。
さらに悪化すると、老廃物が体内に蓄積し、最終的には人工透析が必要となる「末期腎不全」に至ります。
③糖尿病性網膜症
高血糖が目の網膜の細い血管を傷つけ、視力に影響が出る病気です。
初期には自覚症状がありませんが、進行すると網膜に出血やむくみが起こり、視力低下、飛蚊症(目の前にゴミのようなものが見える)、視野の欠損などが現れます。
最悪の場合、失明に至ることもあります。糖尿病患者の失明原因のトップです。
高血糖が目の網膜の細い血管を傷つけ、視力に影響が出る病気です。
初期には自覚症状がありませんが、進行すると網膜に出血やむくみが起こり、視力低下、飛蚊症(目の前にゴミのようなものが見える)、視野の欠損などが現れます。
最悪の場合、失明に至ることもあります。糖尿病患者の失明原因のトップです。

その他の合併症
三大合併症以外にも、高血糖により、心筋梗塞や脳梗塞、末梢動脈疾患といった合併症を招くリスクがあります。
これらの合併症は、糖尿病の怖い側面であり、自覚症状がない段階から血糖値を適切に管理することの重要性を示しています。定期的な健康診断や専門医による診察が、合併症の早期発見と予防には不可欠です。
三大合併症以外にも、高血糖により、心筋梗塞や脳梗塞、末梢動脈疾患といった合併症を招くリスクがあります。
これらの合併症は、糖尿病の怖い側面であり、自覚症状がない段階から血糖値を適切に管理することの重要性を示しています。定期的な健康診断や専門医による診察が、合併症の早期発見と予防には不可欠です。
糖尿病の治療
糖尿病の治療は、単に血糖値を下げるだけでなく、血糖値を適切にコントロールすることで、将来的な神経障害、腎症、網膜症といった合併症の発症や進行を抑制し、健康寿命を延ばすことを最大の目的とします。
治療は、まず生活習慣の改善が基本となり、それでも目標とする血糖値に達しない場合や、病状の進行度合いによっては薬物療法が検討されます。
近年、『臨床的寛解』という考え方が浸透してきています。2型糖尿病の確定診断がされる頃には、すでに膵臓の機能の半分は失われていることがわかってきました。そして、その後の治療期間が長いほど膵臓の機能は失われていく傾向があると考えられています。したがって、発症早期に積極的な治療を行うことで、臨床的寛解まで回復することができ、薬物治療が必要なくなる可能性があります。ただし、その後も食事・運動・体重管理などは必要となります。
治療は、まず生活習慣の改善が基本となり、それでも目標とする血糖値に達しない場合や、病状の進行度合いによっては薬物療法が検討されます。
近年、『臨床的寛解』という考え方が浸透してきています。2型糖尿病の確定診断がされる頃には、すでに膵臓の機能の半分は失われていることがわかってきました。そして、その後の治療期間が長いほど膵臓の機能は失われていく傾向があると考えられています。したがって、発症早期に積極的な治療を行うことで、臨床的寛解まで回復することができ、薬物治療が必要なくなる可能性があります。ただし、その後も食事・運動・体重管理などは必要となります。

治療の目標
糖尿病治療の目標は、患者さんの状態によって異なりますが、一般的には以下の数値を目指します。
HbA1c(ヘモグロビン・エーワンシー)
過去1〜2ヶ月の血糖値の平均を反映する指標です。一般的に、合併症予防のためには7.0%未満が目標とされます。ただし、糖尿尿病発症早期の方は積極的に正常値をめざした治療をすることで臨床的寛解につながる可能性があります。また、高齢者や合併症が進んでいる方の場合には、やや緩めの血糖管理にするなど、個々の状況に合わせて目標値は調整されます。
血糖値
空腹時血糖値: 130mg/dL未満食後2時間血糖値: 180mg/dL未満
これらの目標値を達成し、維持することが、合併症の予防に繋がります。
過去1〜2ヶ月の血糖値の平均を反映する指標です。一般的に、合併症予防のためには7.0%未満が目標とされます。ただし、糖尿尿病発症早期の方は積極的に正常値をめざした治療をすることで臨床的寛解につながる可能性があります。また、高齢者や合併症が進んでいる方の場合には、やや緩めの血糖管理にするなど、個々の状況に合わせて目標値は調整されます。
血糖値
空腹時血糖値: 130mg/dL未満食後2時間血糖値: 180mg/dL未満
これらの目標値を達成し、維持することが、合併症の予防に繋がります。
生活習慣の改善
2型糖尿病において、生活習慣の改善は治療の基盤であり、非常に重要です。1型糖尿病でも、血糖コントロールを安定させるために生活習慣の工夫は必要です。
食事療法
血糖値を直接的に左右するため、食事療法は糖尿病治療の要です。
適正なエネルギー量の摂取
食べ過ぎは血糖値上昇と肥満の原因になります。年齢、性別、身体活動量に応じて、適切なエネルギー量(カロリー)を設定し、それを守ることが基本です。
バランスの取れた食事
炭水化物、タンパク質、脂質をバランス良く摂ることが大切です。特に、血糖値に影響しやすい炭水化物の摂取量と質に注意します。
炭水化物は食事全体のエネルギーの50〜60%程度を目安とし、精製度の低い複合糖質(玄米、全粒粉パン、そばなど)を選ぶと、血糖値の急激な上昇を抑えられます。
食物繊維が多く含まれる、野菜、きのこ、海藻類、こんにゃく、豆類などを毎食摂り、糖の吸収を緩やかにし、血糖値の急上昇を抑えましょう。
ゆっくりよく噛んで食べる
早食いは血糖値の急上昇を招きます。時間をかけてゆっくり食べることで、満腹感も得られやすくなります。
アルコールの制限
アルコールは高カロリーであり、種類によっては糖質も含まれるため、血糖値に影響します。また、肝臓に負担をかけ、低血糖のリスクを高めることもあります。医師と相談し、適量を守りましょう。
食事療法
血糖値を直接的に左右するため、食事療法は糖尿病治療の要です。
適正なエネルギー量の摂取
食べ過ぎは血糖値上昇と肥満の原因になります。年齢、性別、身体活動量に応じて、適切なエネルギー量(カロリー)を設定し、それを守ることが基本です。
バランスの取れた食事
炭水化物、タンパク質、脂質をバランス良く摂ることが大切です。特に、血糖値に影響しやすい炭水化物の摂取量と質に注意します。
炭水化物は食事全体のエネルギーの50〜60%程度を目安とし、精製度の低い複合糖質(玄米、全粒粉パン、そばなど)を選ぶと、血糖値の急激な上昇を抑えられます。
食物繊維が多く含まれる、野菜、きのこ、海藻類、こんにゃく、豆類などを毎食摂り、糖の吸収を緩やかにし、血糖値の急上昇を抑えましょう。
ゆっくりよく噛んで食べる
早食いは血糖値の急上昇を招きます。時間をかけてゆっくり食べることで、満腹感も得られやすくなります。
アルコールの制限
アルコールは高カロリーであり、種類によっては糖質も含まれるため、血糖値に影響します。また、肝臓に負担をかけ、低血糖のリスクを高めることもあります。医師と相談し、適量を守りましょう。
運動療法
運動は、インスリンの効果を高め、血糖値を下げるだけでなく、肥満の解消やストレス解消にも繋がります。
有酸素運動
ウォーキング、ジョギング、水泳、サイクリングなど、酸素を取り込みながら行う運動が効果的です。筋肉がブドウ糖をエネルギーとして消費するため、血糖値が下がります。
週に3〜5回、1回あたり20〜60分程度行うのが目安です。可能であれば毎日継続することが理想です。
筋力トレーニング
筋肉量を増やすことで、基礎代謝が上がり、血糖値を下げる効果も期待できます。有酸素運動と組み合わせて行うとより効果的です。
【運動の注意点】
血糖値が極端に高い場合や、合併症が進んでいる場合は、運動が危険なこともあります。運動を始める前に必ず医師に相談し、適切な運動の種類や強度を確認しましょう。
運動は、インスリンの効果を高め、血糖値を下げるだけでなく、肥満の解消やストレス解消にも繋がります。
有酸素運動
ウォーキング、ジョギング、水泳、サイクリングなど、酸素を取り込みながら行う運動が効果的です。筋肉がブドウ糖をエネルギーとして消費するため、血糖値が下がります。
週に3〜5回、1回あたり20〜60分程度行うのが目安です。可能であれば毎日継続することが理想です。
筋力トレーニング
筋肉量を増やすことで、基礎代謝が上がり、血糖値を下げる効果も期待できます。有酸素運動と組み合わせて行うとより効果的です。
【運動の注意点】
血糖値が極端に高い場合や、合併症が進んでいる場合は、運動が危険なこともあります。運動を始める前に必ず医師に相談し、適切な運動の種類や強度を確認しましょう。
その他の生活習慣
禁煙
喫煙はインスリン抵抗性を悪化させ、糖尿病の合併症(特に動脈硬化)のリスクを大幅に高めます。糖尿病患者にとって、禁煙は必須です。
口腔ケア
糖尿病患者は歯周病のリスクが高く、歯周病が悪化すると血糖コントロールも悪化する悪循環に陥ります。毎日の丁寧な歯磨きと定期的な歯科受診が重要です。
禁煙
喫煙はインスリン抵抗性を悪化させ、糖尿病の合併症(特に動脈硬化)のリスクを大幅に高めます。糖尿病患者にとって、禁煙は必須です。
口腔ケア
糖尿病患者は歯周病のリスクが高く、歯周病が悪化すると血糖コントロールも悪化する悪循環に陥ります。毎日の丁寧な歯磨きと定期的な歯科受診が重要です。
薬物療法
生活習慣の改善だけでは目標血糖値に達しない場合や、病状が進んでいる場合には、薬物療法が開始されます。糖尿病の薬には様々な種類があり、患者さんの状態や糖尿病のタイプに合わせて使い分けられます。
経口血糖降下薬
2型糖尿病の治療で最も一般的に用いられる飲み薬です。様々な作用メカニズムを持つ薬があります。
GLP-1受容体作動薬
インクレチンに似た作用を持つ注射薬で、血糖値に応じてインスリン分泌を促し、食欲を抑える効果もあります。体重減少効果も期待できるため、肥満を伴う2型糖尿病患者さんに使われることがあります。
インスリン療法
1型糖尿病では必須の治療法です。2型糖尿病でも、経口薬や他の注射薬で血糖コントロールが難しい場合や、膵臓の機能が低下している場合に導入されます。インスリンを直接体内に補給することで、血糖値を下げます。インスリンの種類や注射回数、量は患者さんの状態に合わせて細かく調整されます。
生活習慣の改善だけでは目標血糖値に達しない場合や、病状が進んでいる場合には、薬物療法が開始されます。糖尿病の薬には様々な種類があり、患者さんの状態や糖尿病のタイプに合わせて使い分けられます。
経口血糖降下薬
2型糖尿病の治療で最も一般的に用いられる飲み薬です。様々な作用メカニズムを持つ薬があります。
- インスリン分泌促進薬: 膵臓からのインスリン分泌を促す薬です。
- インスリン抵抗性改善薬: 筋肉や脂肪組織でのインスリンの効き目を良くする薬です。
- 糖吸収・排泄調節薬: 腸からの糖の吸収を遅らせたり、腎臓からの糖の排泄を促進したりする薬です。
- DPP-4阻害薬: 血糖値に応じてインスリン分泌を促すホルモン(インクレチン)を分解する酵素の働きを抑え、インクレチンの作用を強める薬です。
GLP-1受容体作動薬
インクレチンに似た作用を持つ注射薬で、血糖値に応じてインスリン分泌を促し、食欲を抑える効果もあります。体重減少効果も期待できるため、肥満を伴う2型糖尿病患者さんに使われることがあります。
インスリン療法
1型糖尿病では必須の治療法です。2型糖尿病でも、経口薬や他の注射薬で血糖コントロールが難しい場合や、膵臓の機能が低下している場合に導入されます。インスリンを直接体内に補給することで、血糖値を下げます。インスリンの種類や注射回数、量は患者さんの状態に合わせて細かく調整されます。
合併症の管理
糖尿病の治療は、血糖コントロールだけでなく、合併症の早期発見と予防、進行抑制も重要です。
糖尿病の治療は、長期にわたる取り組みが必要ですが、自己管理をしっかり行い、医療機関と連携することで、健康な生活を維持し、合併症のリスクを最小限に抑えることが可能です。
- 定期的な検査: 眼科受診(網膜症のチェック)、尿検査(腎症のチェック)、神経学的検査(神経障害のチェック)などを定期的に行い、合併症の有無や進行度を確認します。
- 他の生活習慣病の管理: 高血圧や脂質異常症は、糖尿病の合併症(特に動脈硬化)のリスクをさらに高めます。これらの病気も同時に治療し、適切に管理することが重要です。
糖尿病の治療は、長期にわたる取り組みが必要ですが、自己管理をしっかり行い、医療機関と連携することで、健康な生活を維持し、合併症のリスクを最小限に抑えることが可能です。

